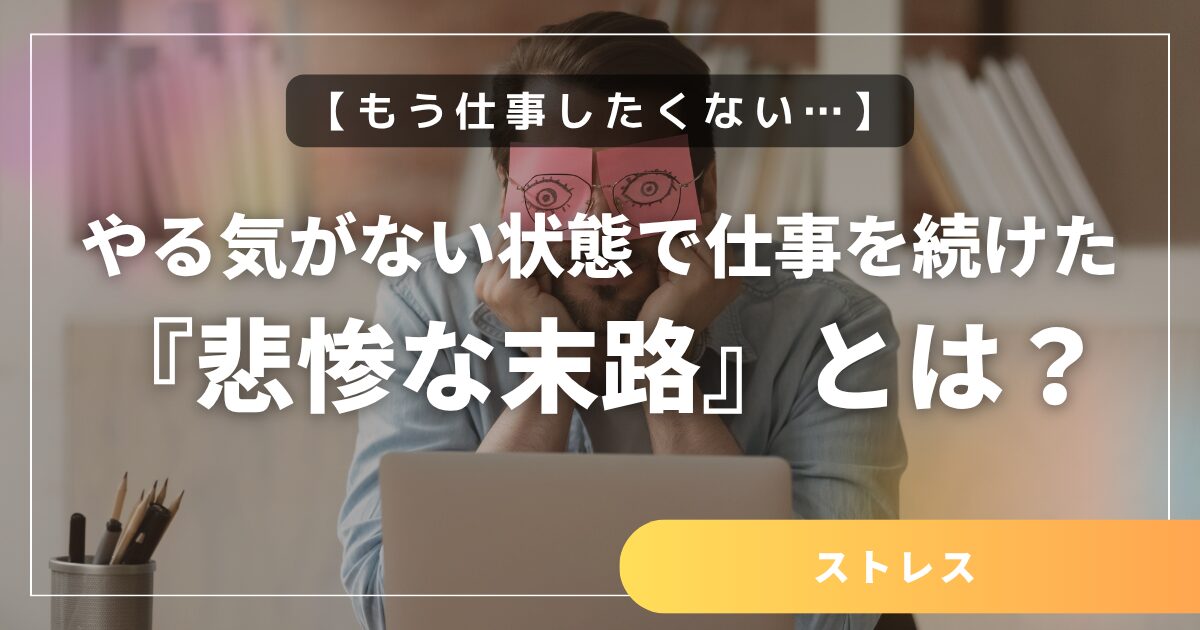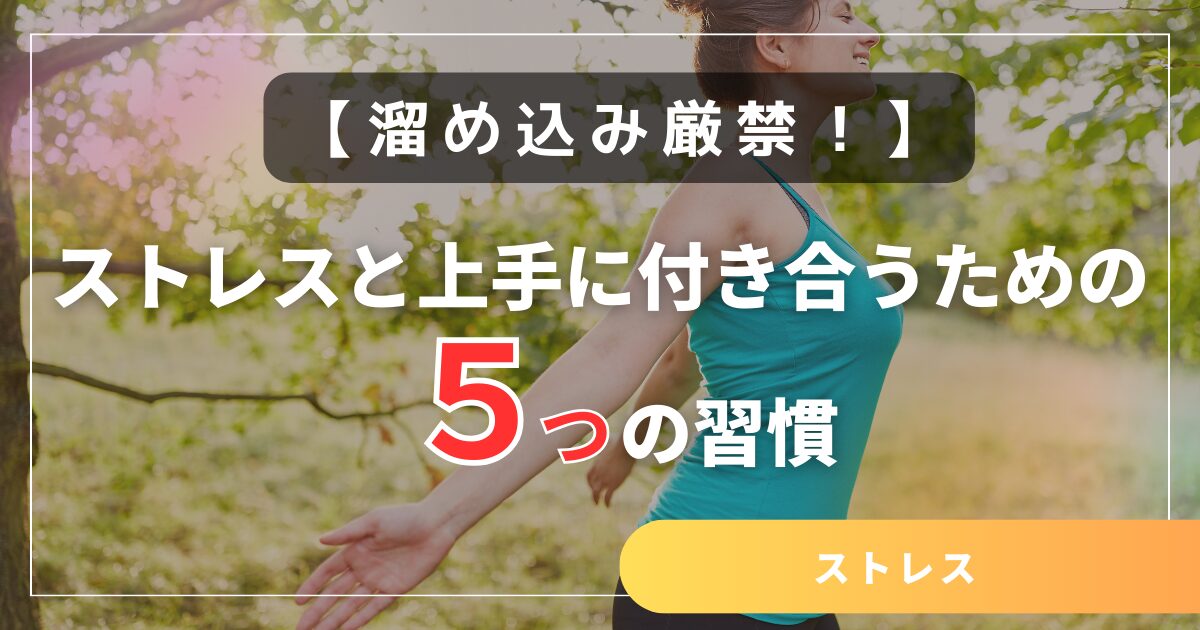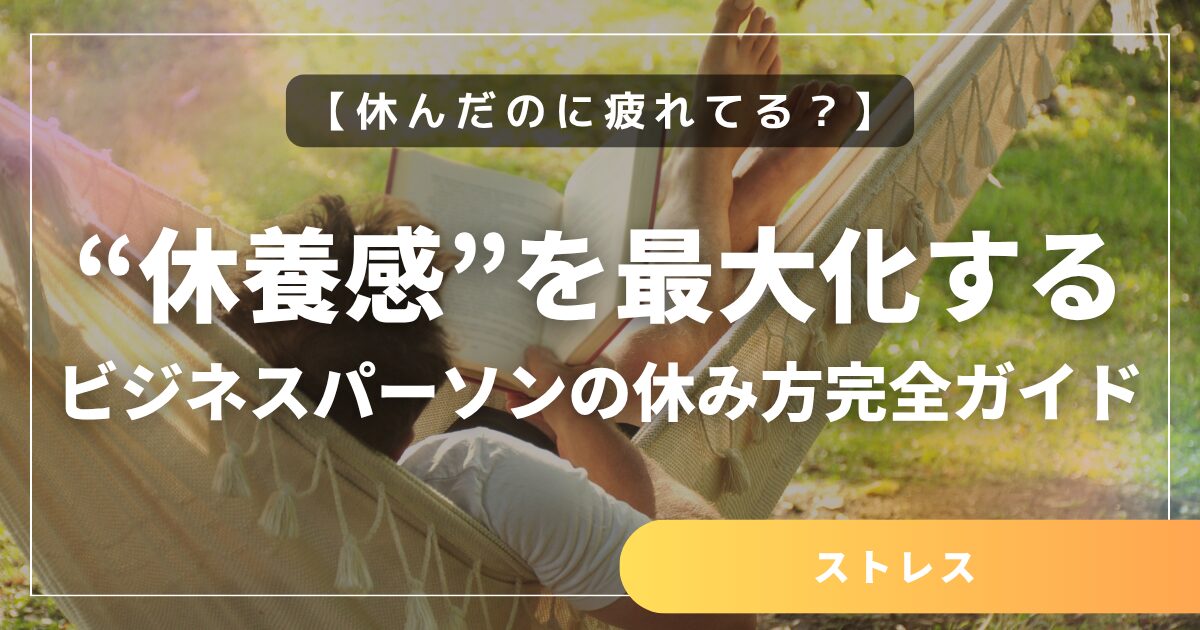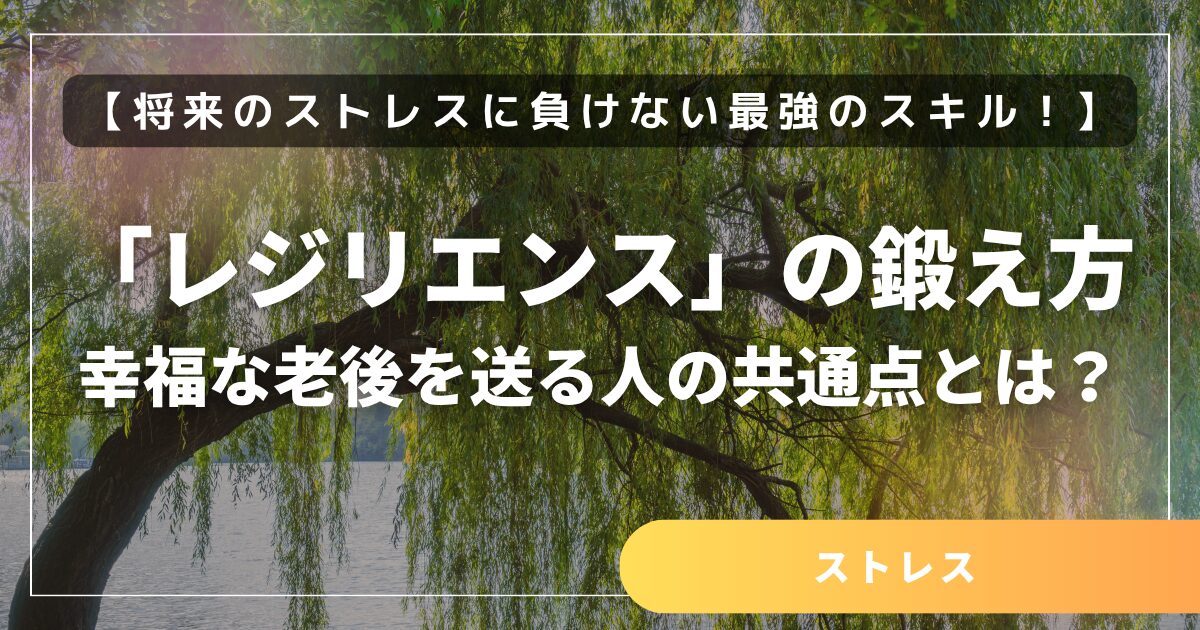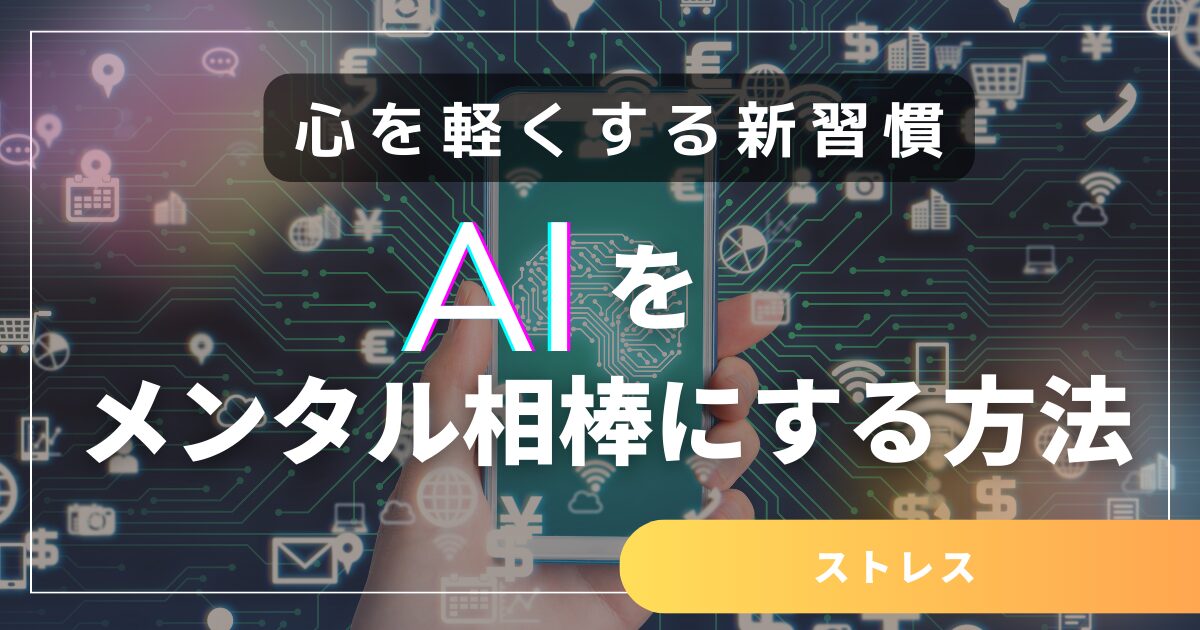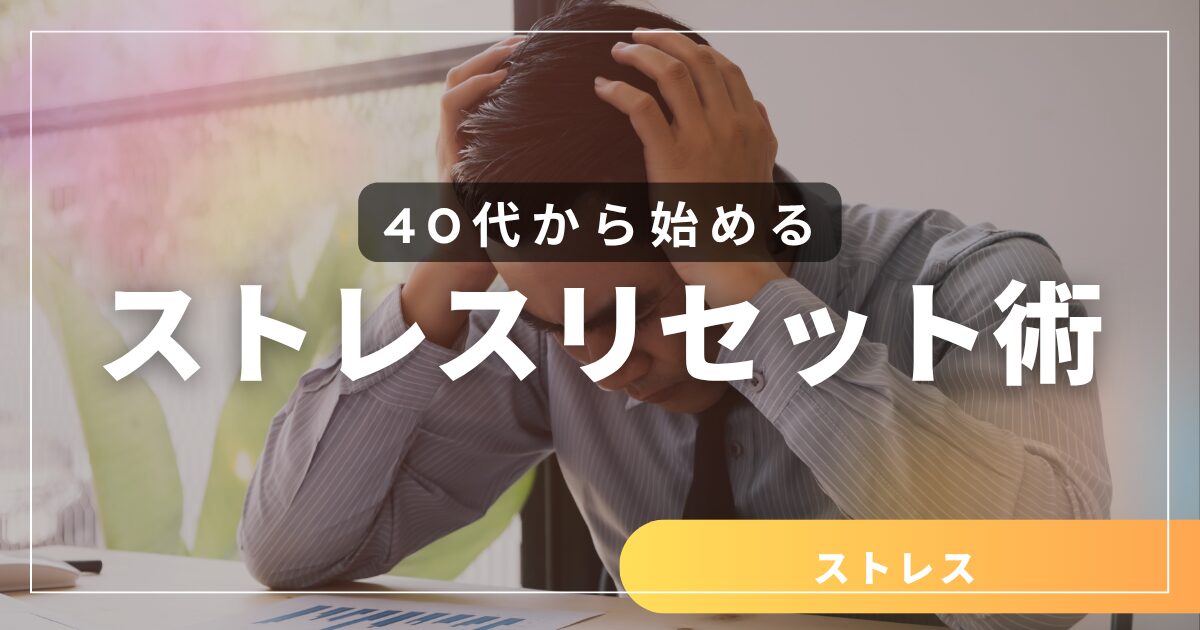もう落ち込まない!「リフレーミング」でストレスを力に変える思考術
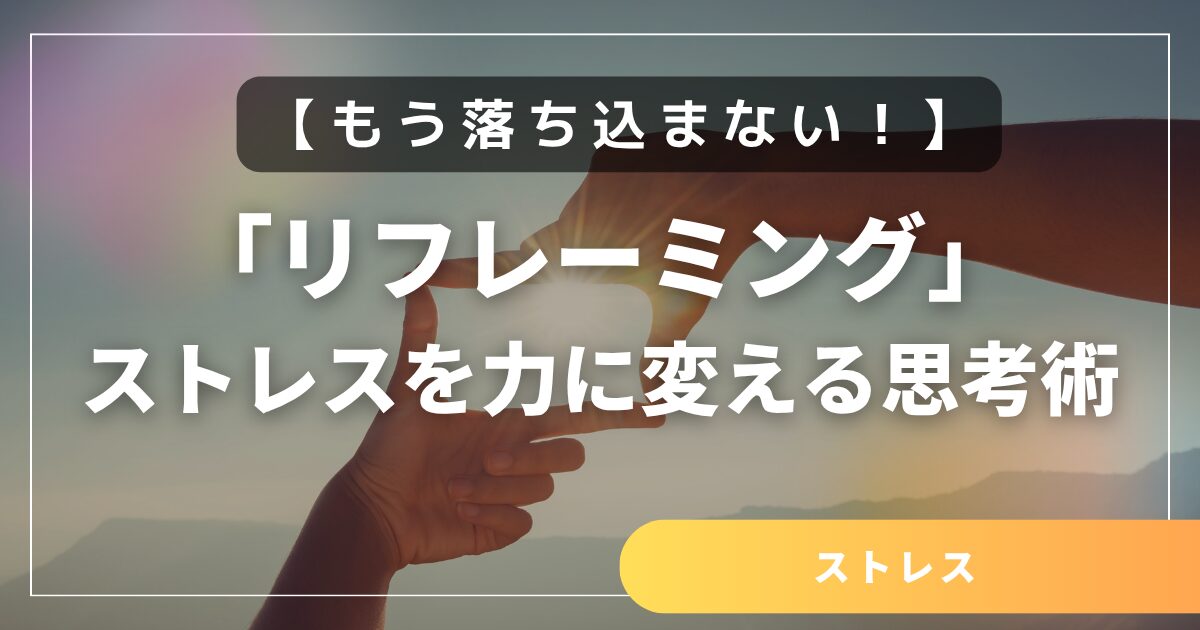
仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、思うようにいかない現実…。私たちは日々、様々なストレスにさらされています。
「また落ち込んでしまった」「自分はストレスに弱いな…」と感じることも多いかもしれません。
しかし、もしそのストレスを、自分を成長させてくれる「力」に変える方法があるとしたら、知りたくありませんか?
この記事では、心理学の世界で注目されている思考法「リフレーミング」について、その科学的な効果から、初心者でも今日から始められる具体的な実践方法を解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたの心は少し軽くなり、ストレスに対する新しい向き合い方が身についているはずです。
そもそも「リフレーミング」って、一体何?

リフレーミング(Reframing)とは、その名の通り、出来事を捉える「フレーム(Frame)=枠組み」を「リ(Re)=再び」設定し直すことです。
例えば、同じ一枚の絵でも、暗い色の額縁に入れるのと、明るい色の額縁に入れるのとでは、絵全体の印象がガラリと変わりますよね。
これと同じように、目の前で起きた出来事(絵)に対する解釈の枠組み(額縁)を変えることで、そこから生まれる感情を意図的に変化させる。これがリフレーミングの基本的な考え方です。
もっと身近な言葉で言うなら「心のメガネをかけ替える技術」と考えると分かりやすいかもしれません。
「心のメガネってことは…ブルーライトカットより“イライラカット”が必要ってことっすね?」

「そうそう。レンズを変えるだけで、同じ景色でも見え方が変わるのよ。」

事実は一つ、でも「解釈」は無限大。感情が生まれる本当の理由

心理学では、私たちの感情は「起きた出来事」によって直接決まるのではなく、その出来事を「どう解釈したか」によって決まると考えられています。
「コップに半分の水」の有名な話をご存知でしょうか。「もう半分しかない」と嘆くか、「まだ半分もある」と喜ぶか。水が半分入っているという事実は一つですが、それをどう捉えるかという解釈は無限にあるのです。
これは仕事の場面でも同じです。
例えば、「上司に厳しいフィードバックをされた」という事実があったとします。
「自分は全く評価されていないんだ…。この仕事に向いていないのかもしれない」
生まれる感情: 落ち込み、無力感、不安
「それだけ真剣に見てくれている証拠だ。期待されているからこそのアドバイスだな」
生まれる感情: やる気、感謝、少しの悔しさ
このように、同じ出来事を経験しても、どんな「心のメガネ」を通して見るかによって、世界は全く違って見えるのです。
ストレスを感じやすい人は、無意識のうちに少し曇った、物事をネガティブに見せてしまうメガネをかけているのかもしれません。
「事実と解釈を切り分けるだけで、感情の暴走は止めやすくなる。まずは“今のは解釈だ”と気づくところからだ。」

ポジティブ思考とは違うの?リフレーミングが持つ本当の力
「じゃあ、何でも前向きに考えればいいの?」と思うかもしれませんが、リフレーミングは無理やりポジティブになる「ポジティブシンキング」とは少し違います。
むしろ、曇っていたり歪んでいたりする「心のメガネ」を一度外し、丁寧に拭いて、物事を多角的かつ現実的に見るための技術です。無理にバラ色のメガネをかける必要はありません。
時には、無理にポジティブに解釈せず、「今は悲しいし、落ち込んでも当然の状況だ」と自分の感情をありのまま認めることも、心を健全に保つための重要なリフレーミングの一つなのです。
大切なのは、一つのネガティブな解釈に心を縛り付けられず、「他の見方もできるんだ」と心の選択肢を増やすこと。その心の柔軟性こそが、リフレーミングの持つ本当の力です。
「“何でもポジティブに!”は現実逃避になりがち。等身大の見直しが、いちばん効果的です。」

なぜ視点を変えるだけで心が楽になるの?科学が解き明かすリフレーミングの効果

「考え方を変えるだけで楽になるなんて、気休めじゃないの?」と半信半疑に思うかもしれません。
しかし、リフレーミングの効果は、気合や根性論ではなく、様々な研究によって科学的にもその仕組みが解き明かされつつあります。
ここでは、あなたの脳と心に起こるポジティブな変化を、3つの研究結果からご紹介します。
【理由①】ストレスに対する「心構え」が変わるから
とても面白い心理学の実験があります。これからストレスのかかる課題に挑戦してもらう人たちを、2つのグループに分けました。
Aグループには「ストレスは体に悪いですよ」とだけ伝える。
Bグループには「ストレスには悪い面もあるけれど、集中力を高めるなど良い面もあるんですよ」と伝える。
すると、心拍数や血圧などの反応が穏やかだったのは、断然Bグループでした。
この結果からわかるのは、「ストレスに対する思い込み(心構え)が、実際の体の反応を変える」ということです。
リフレーミングは、まさにこの「Bグループの心構え」を、自分自身の力で作るためのトレーニングです。
「ストレス=100%敵!」という硬直した考え方から、「味方になる側面もあるかも?」と視点を変えることで、脳の過剰な警戒アラームが鳴り止み、冷静に対応できるようになるのです。
「ストレスは敵だ」という思い込みを手放し、「自分の力になる資源だ」と捉え直してみる。こうした心構えの変化が、体にも影響してくるんだ。

【理由②】練習の効果が翌週にも持続するから
リフレーミングは、一度身につければ持続的に効果を発揮する「心のスキル」です。
その証拠に、ある研究では興味深い「時間差効果」が報告されています。それは、リフレーミングを練習した週の、さらに翌週に不安感が軽減されるというものです。
これは、練習がその場限りの気休めで終わるのではなく、じっくりと心に浸透し、安定した状態を作り出していることを意味します。
体のトレーニングと同様、即効性を期待するものではないかもしれません。しかし、練習を続けた分だけ、あなたの心は確実にストレスへの耐性を高めていくでしょう。
「翌週に効果が出るって、筋トレの超回復みたいでワクワクするっす!」

【理由③】「自分なら大丈夫」という“心の成功体験”が自信を育てるから
研究でわかってきたのは、リフレーミングの本当の価値は、テクニックそのもの以上に「自分なら大丈夫」という自信(自己効力感)を育ててくれる点にある、ということです。
例えば、「イラっとしたけど、見方を変えたら少し落ち着けた」という体験。
こんな小さな成功体験が、「自分は感情に振り回されるだけじゃない、ちゃんと主導権を握れるんだ」という感覚を脳に刻んでくれます。
この積み重ねによって育まれた自信こそが、次に大きなストレスが来た時にあなたを守ってくれる、大切な心の資産になっていきます。
試しに挑戦!リフレーミング練習法

リフレーミングが時に難しく感じるのは、私たちの思考が長年の「クセ」によって、ある程度自動化されているからです。
そのため、新しい思考法を身につけるには、スポーツや楽器の練習のように反復が欠かせません。
嬉しいことに、この練習には「続けた分だけ、未来の不安が軽くなる」という科学的な裏付けもあります。焦らず、ご自身のペースで取り組んでいきましょう。
【Step 1:基礎編】言葉の言い換えトレーニング
いきなり大きな悩みで試そうとすると、難しくて挫折しがちです。まずは、頭の準備運動として、簡単な言葉の言い換えゲームから始めてみましょう。
あなたが自分の短所だと思っている言葉を、長所に言い換える練習です。これは「リバーシブル思考」とも呼ばれ、多角的な視点を養う第一歩になります。
「飽きっぽい」 → 「好奇心旺盛で、新しいことへの挑戦が早い」
「心配性」 → 「危機管理能力が高い、慎重で準備を怠らない」
「頑固」 → 「意志が強く、自分の信念を持っている」
普段、無意識に口にしているネガティブな言葉を、意識的に別の言葉に置き換えてみましょう。言葉が変わると、脳が受け取る印象も変わります。
「疲れた…」 → 「今日もよく頑張ったな」「充実した一日だった」
「時間がない!」 → 「どうすれば効率的にできるかな?」
「どうせ無理だ」 → 「どうやったらできるだろう?」「まずは試してみよう」
【Step 2:応用編】日常の「モヤッと」を題材にする
言葉の言い換えに慣れてきたら、次は日常生活で実際に感じる小さなストレスを題材に練習してみましょう。
満員電車や、なかなか終わらない家事など、日常には小さなイライラの種がたくさんあります。これらは絶好の練習材料です。
【出来事】 電車が遅延している
【最初の解釈】「またかよ、最悪だ…」
【リフレーミング】「おかげで少し読書が進むな」「急がなくていい、と神様が言っているのかも」
友人のキラキラした投稿を見て、心がザワっとすることはありませんか?その感情を否定せず、「なぜ自分はそう感じるんだろう?」と分析し、リフレーミングしてみましょう。
【出来事】 同期の昇進報告を見た
【最初の解釈】「それに比べて自分は…」と落ち込む
【リフレーミング】「身近に目標となる人がいてラッキーだ」「自分も頑張ろうと刺激をもらえた」
【Step 3:発展編】「書き出す」ことで思考を客観視する
頭の中だけで考えると、同じ思考がぐるぐる回ってしまうことがあります。そんな時は「書き出す」ことで、自分の考えを客観的に捉え、リフレーミングしやすくなります。
ノートを3つの欄に分け、左から「出来事」「自動思考(最初に浮かんだ感情や考え)」「リフレーミング(別の見方)」を書き出す方法です。
| 出来事 | 自動思考 | リフレーミング |
| 会議で意見を否定された | 私の考えは価値がないんだ | 別の視点をもらえた |
| みんなの前で恥をかいた | 議論が活発になった証拠だ | |
| 次はもっと良い提案をしよう |
寝る前の5分間、その日あった嫌な出来事やモヤっとしたことを1つだけ取り上げ、「もしリフレーミングするなら?」と考えて書き出してみましょう。ネガティブな気持ちで一日を終えるのではなく、心を整えて眠りにつくことができます。
ご紹介した練習法は、どれもすぐに始められる簡単なものばかりです。
大切なのは、完璧を目指さないこと。「うまくできない日があってもいい」と気楽な気持ちで、ゲーム感覚で続けてみてください。
「頭の中だけで回すより、書くと“思考のぐるぐる”が止まりやすいですよ。」

「3コラム法、スマホのメモでもいけますね。続けやすそう!」

日常で使えるリフレーミング実践法
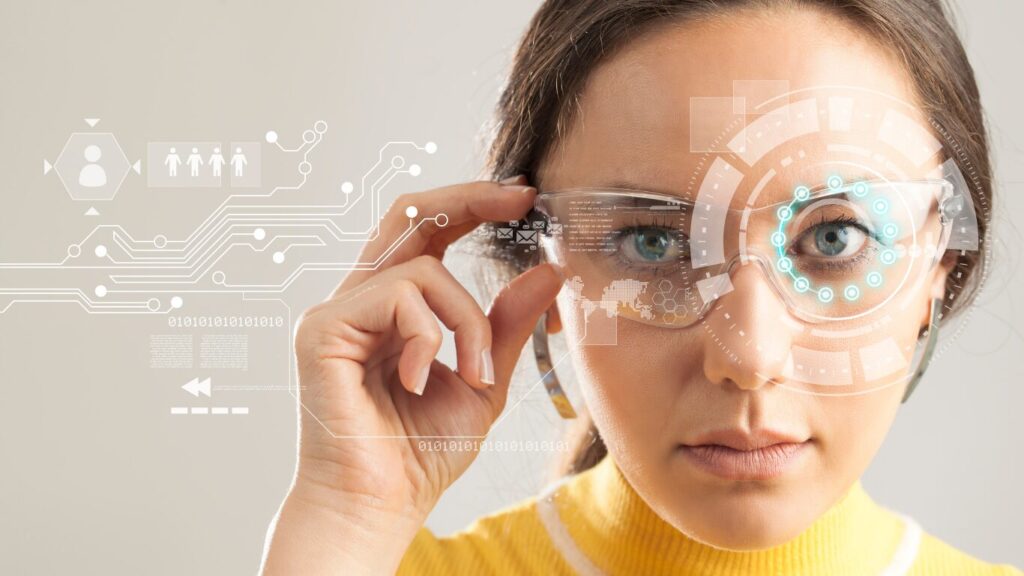
理屈は分かっても、「いざとなるとなかなかできない…」と感じるかもしれませんが、大丈夫です。リフレーミングは、特別な訓練をしなくても、日常のちょっとした言葉遣いや考え方の工夫で実践できます。
ここでは、すぐに試せる簡単な方法をご紹介します。
方法①:「おかげで」と付け足すだけ!“恩恵探し”リフレーミング
どんなに嫌な出来事にも、「〇〇だったけど、おかげで△△を学べた」という言葉を続けてみましょう。これは、ネガティブな出来事の中に隠れている「恩恵」や「学び」を強制的に探し出す練習です。
(例)「急な仕事を頼まれたけど、おかげで新しいスキルを身につけるチャンスができた」
私たちの脳は、一度ネガティブな側面を見ると、そればかりに囚われてしまいがちです。
この方法は、その視点を強制的に切り替え、物事のプラスの側面に光を当てるきっかけを作ってくれます。
「“最悪”って思った瞬間に“恩恵探し”スイッチON…クセにします!」

方法②:「~べき」の呪いを解く!“願望変換”リフレーミング
「早く終わらせるべき」「誰かに迷惑をかけるべきではない」「完璧にやるべきだ」…。こうした「~べき」という思考は、私たちを義務感で縛り付け、大きなストレスを生み出します。
もし「~べき」という言葉が頭に浮かんだら、それを自分の「~したい」という願望に変換してみましょう。
Before:「この資料を今日中に作るべきだ」
After:「この資料を今日中に作って、明日の朝スッキリした気持ちで迎えたい」
行動は同じでも、動機が「義務」から「願望」に変わるだけで、心の負担は驚くほど軽くなるぞ。

【こんな時どうする?】仕事のストレス場面別リフレーミング実践例
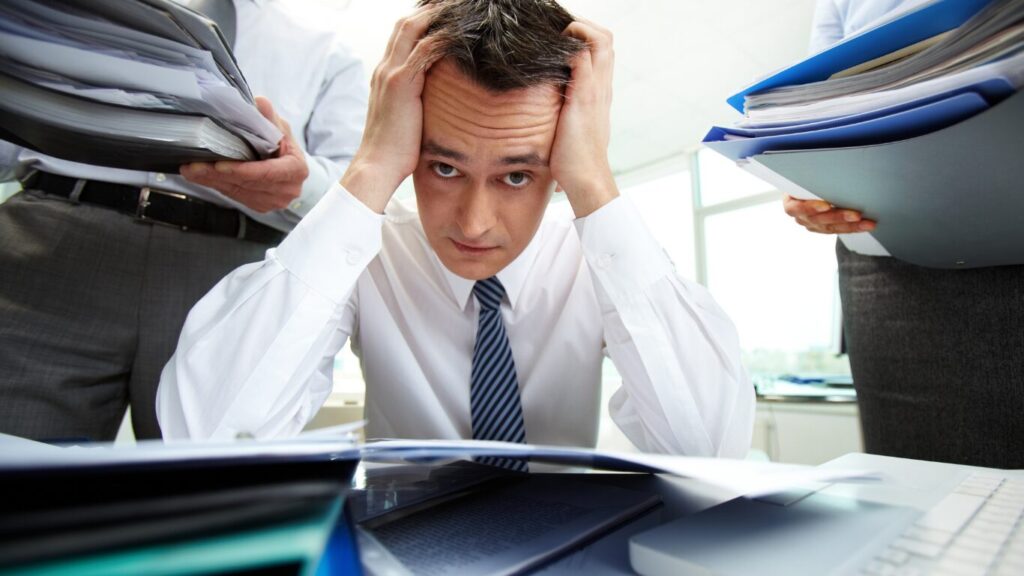
これまでに学んだ方法を、実際のビジネスシーンでどのように活かせるか、具体的な例を見ていきましょう。
頭で理解するだけでなく、実際の場面を想像することで、リフレーミングはより強力なスキルになります。
Case1:仕事で予想外のミスをしてしまった…
【最初の解釈(Before)】
「なんて自分はダメなんだ…。周りに迷惑をかけてしまったし、評価もきっと下がってしまう。もう終わりだ…」
【リフレーミング後(After)】
- 「この段階で失敗に気づけてよかった。おかげで、もっと大きな問題になる前に修正できる」
- 「1年後にはきっと笑い話になっている。この経験のおかげで、未来の自分がもっと大きな失敗を防げるはずだ」
- 「失敗を取り返すべきだ」→「この経験を次に活かして、もっと信頼されるようになりたい」
失敗を「終わり」と捉えるのではなく、「未来への投資」や「学びの機会」と捉え直すことで、自己嫌悪から抜け出し、次への一歩を踏み出すエネルギーが生まれます。
Case2:頑張っているのに、なかなか成果が出ない…
【最初の解釈(Before)】
「自分には才能がないのかもしれない。これ以上やっても無駄だ。周りはどんどん先に進んでいるのに…」
【リフレーミング後(After)】
- 「成果が出ないのは、それだけ自分が難しい課題に挑戦している証拠だ」
- 「この方法ではダメだと分かっただけでも、大きな収穫だ。おかげで、別のアプローチを試すきっかけができた」
- 「もし親友が同じ状況なら、『今は力を蓄える時期だよ』って声をかけるな。自分も焦る必要はないのかもしれない」
成果が出ない時期を「停滞」ではなく、「準備」や「方向転換のチャンス」と捉え直すことで、焦りや無力感を手放し、粘り強く挑戦を続けることができます。
まとめ:リフレーミングは心の筋トレ。今日から始める小さな一歩
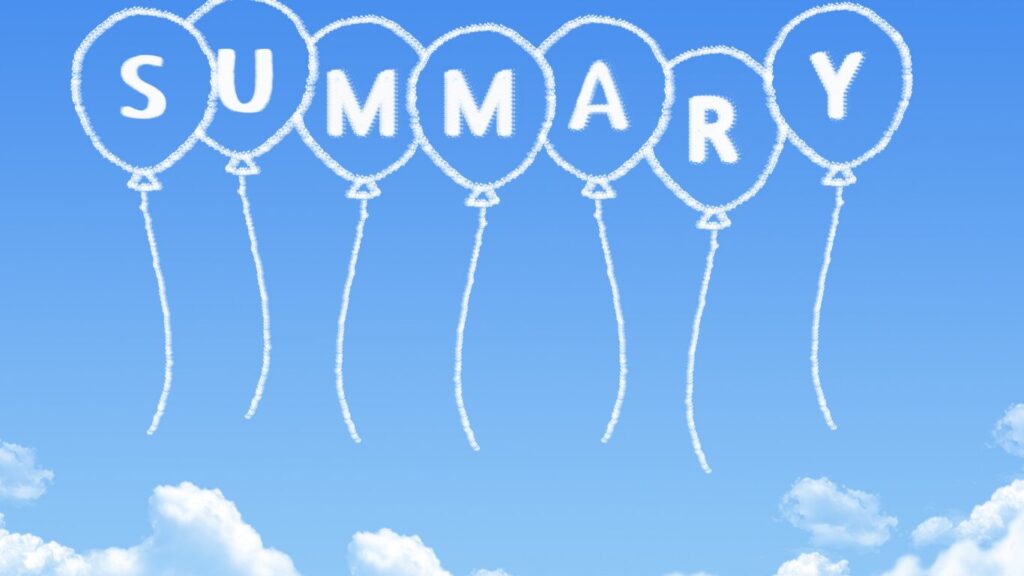
この記事では、ストレスフルな出来事に対する私たちの感情が、「出来事」そのものではなく、それをどう「解釈」するかによって決まる、という心の仕組みから話を始めました。
そして、その「解釈」の枠組みを意図的に変えることで心を軽くする技術、「リフレーミング」をご紹介しました。
リフレーミングは、無理にポジティブになることではありません。ストレスの持つ多面性を理解し、練習を重ねることで持続的な効果を発揮し、「自分なら大丈夫」という自信を育ててくれる、科学的にも裏付けのある「心のスキル」です。
記事の中では、「言葉の言い換え」といった基礎的なトレーニングから、「書き出す」ことで思考を整理する発展的な練習法、そして具体的なビジネスシーンでの実践例までを見てきました。
たくさんの方法をご紹介しましたが、最初からすべてを完璧にやろうとする必要は全くありません。リフレーミングがうまくいかない自分を責めてしまっては、本末転倒です。
大切なのは、「あ、今自分はネガティブに捉えているな」と、自分の心のクセに「気づくこと」。そして、もし心に余裕があれば、「他の見方もできるかな?」と考えてみることです。
まずは今日から1日1回、通勤中の小さなイライラや、寝る前に思い出すモヤモヤした気持ちを一つだけ取り上げて、ご紹介した方法のどれか一つを試してみてください。
その小さな一歩が、未来のあなたをストレスから守る、しなやかで強い心へと繋がっています。
「大事なのは“気づいて、選び直す”の反復だ。小さな反復が、やがて大きな自信になる。」

「了解っす!まずは“電車の遅延=読書のチャンス”から始めます!」

参考リンク
この記事の参考論文はコチラ
Bryant RA, Azevedo S, Yadav S, Cahill C, Kenny L, Maccallum F, Tran J, Choi-Christou J, Rawson N, Tockar J, Garber B, Keyan D, Dawson KS. Cognitive Behavior Therapy vs Mindfulness in Treatment of Prolonged Grief Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2024 Jul 1;81(7):646-654. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2024.0432. PMID: 38656428; PMCID: PMC11044011.
Goldin PR, Thurston M, Allende S, Moodie C, Dixon ML, Heimberg RG, Gross JJ. Evaluation of Cognitive Behavioral Therapy vs Mindfulness Meditation in Brain Changes During Reappraisal and Acceptance Among Patients With Social Anxiety Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2021 Oct 1;78(10):1134-1142. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2021.1862. PMID: 34287622; PMCID: PMC8295897.
Goldin PR, Thurston M, Allende S, Moody C, Dixon ML, Heimberg RG, Gross JJ. A Comparison of Cognitive Behavioral Group Therapy and Mindfulness-Based Stress Reduction on Brain Changes During Reappraisal and Acceptance in Patients With Social Anxiety Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2021 Jul 21;78(10):1134-1142. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2021.1862. PMID: 34287622; PMCID: PMC8295897.
Bryant RA, Azevedo S, Yadav S, Cahill C, Kenny L, Maccallum F, Tran J, Choi-Christou J, Lawson N, Tocker J, Gerber B, Keeyan D, Dawson KS. A Comparison of Cognitive Behavior Therapy vs Mindfulness for the Treatment of Prolonged Grief Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2024 Apr 24;81(7):646-654. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2024.0432. PMID: 38656428; PMCID: PMC11044011
Hamza J, Vytykačová S, Janšáková K, Rajčáni J. Cognitive reappraisal and acceptance following acute stress. Stress Health. 2024 Sep 4. doi: 10.1002/smi.3469. Epub ahead of print. PMID: 39228514.
Marciniak MA, Homan S, Zerban M, Schrade G, Yuen KSL, Kobylińska D, Wieser MJ, Walter H, Hermans EJ, Shanahan L, Kalisch R, Kleim B. Positive cognitive reappraisal flexibility is associated with lower levels of perceived stress. Behav Res Ther. 2024 Dec;183:104653. doi: 10.1016/j.brat.2024.104653. Epub 2024 Jul 31.
Zweerings J, Sarkheil P, Keller M, Dyck M, Klasen M, Becker B, Gaebler AJ, Ibrahim CN, Turetsky BI, Zvyagintsev M, Flatten G, Mathiak K. Rt-fMRI neurofeedback-guided cognitive reappraisal training modulates amygdala responsivity in posttraumatic stress disorder. Neuroimage Clin. 2020 Oct 28;28:102483. doi: 10.1016/j.nicl.2020.102483. PMID: 33395974; PMCID: PMC768941
Hallford DJ, Hardgrove S, Sanam M, Oliveira S, Pilon M, Duran T. Remembering for resilience: Brief cognitive-reminiscence therapy improves psychological resources and mental well-being in young adults. Appl Psychol Health Well Being. 2022 Sep;14(3):1004-1021. doi: 10.1111/aphw.12364. Epub 2022 May 2. PMID: 35502002; PMCID: PMC9545317
Guendelman S, Bayer M, Prehn K, Dziobek I. Towards a mechanistic understanding of mindfulness-based stress reduction (MBSR) using an RCT neuroimaging approach: Effects on regulating own stress in social and non-social situations. Neuroimage. 2022 Jul 1;254:119059. doi: 10.1016/j.neuroimage.2022.119059. Epub 2022 Mar 22. PMID: 35331923; PMCID: PMC9119565
Liu JJW, Reed M, Vickers K. Reframing the individual stress response: Balancing our knowledge of stress to improve responsivity to stressors. Stress Health. 2019 Dec;35(5):607-616. doi: 10.1002/smi.2893. Epub 2019 Aug 20. PMID: 31429995.
Goldin PR, Morrison AS, Jazaieri H, Heimberg RG, Gross JJ. Trajectories of Social Anxiety, Cognitive Reappraisal, and Mindfulness During an RCT of CBGT versus MBSR for Social Anxiety Disorder. Behav Res Ther. 2017 Jun 3;97:1-13. doi: 10.1016/j.brat.2017.06.001. Epub 2017 Jun 8. PMID: 28654771; PMCID: PMC5600696
Bowers EM, Levin ME, Ong CW, Twohig MP. A randomized controlled trial of self-help acceptance and commitment therapy and cognitive behavioral therapy for perfectionism. Behav Res Ther. 2025 Sep;192:104806. doi: 10.1016/j.brat.2025.104806. Epub 2025 Jul 1.