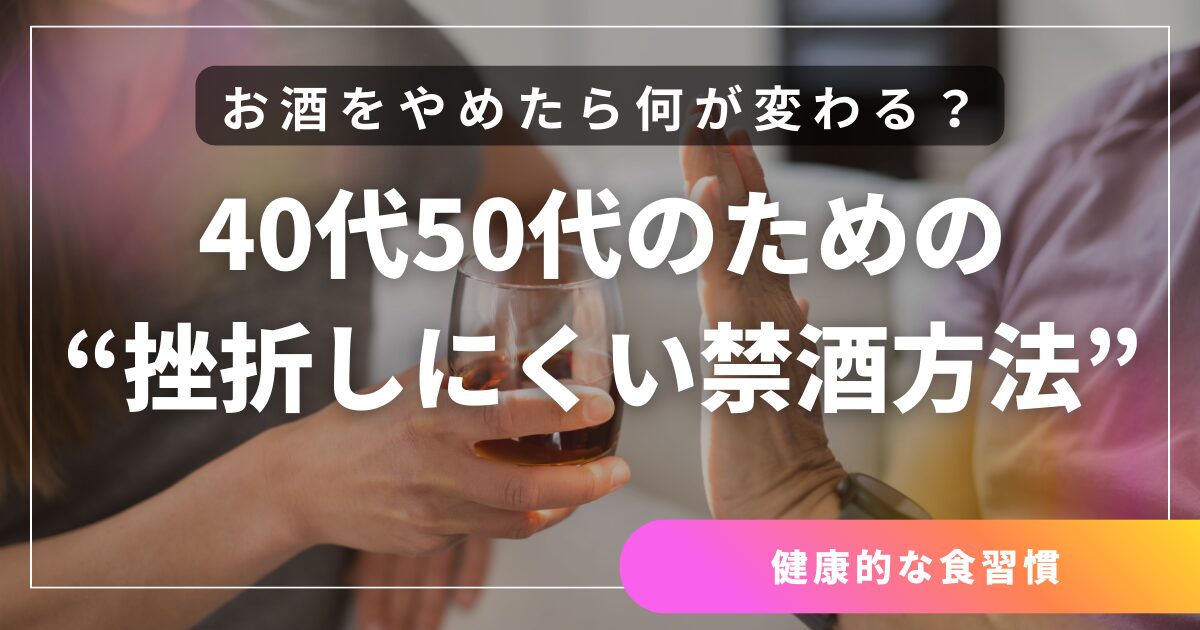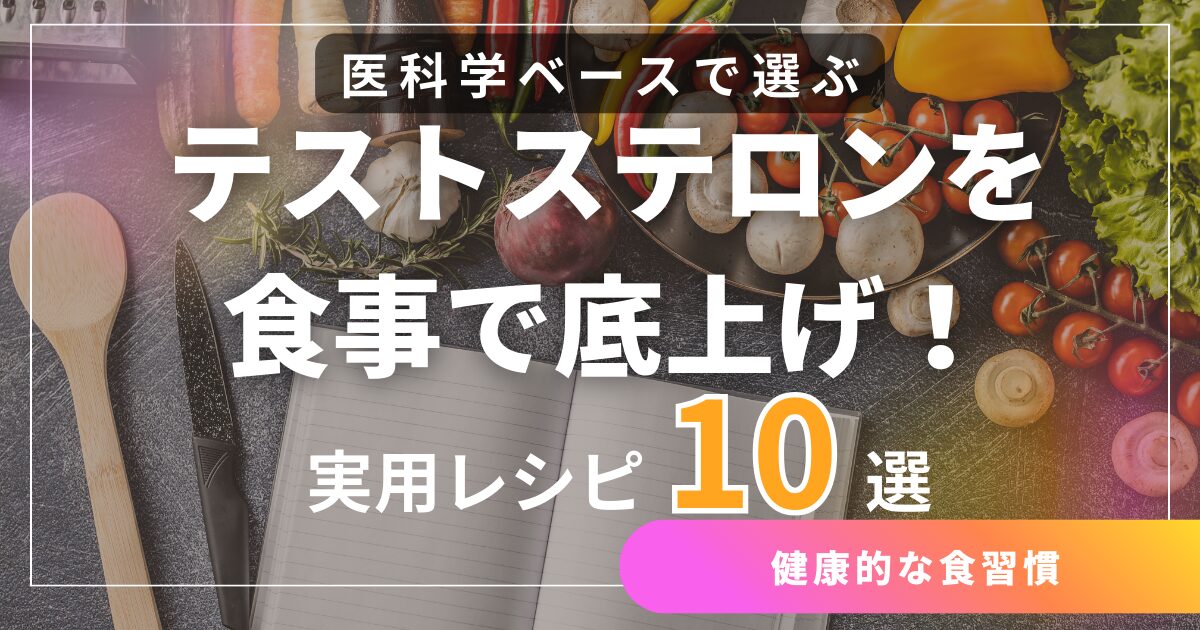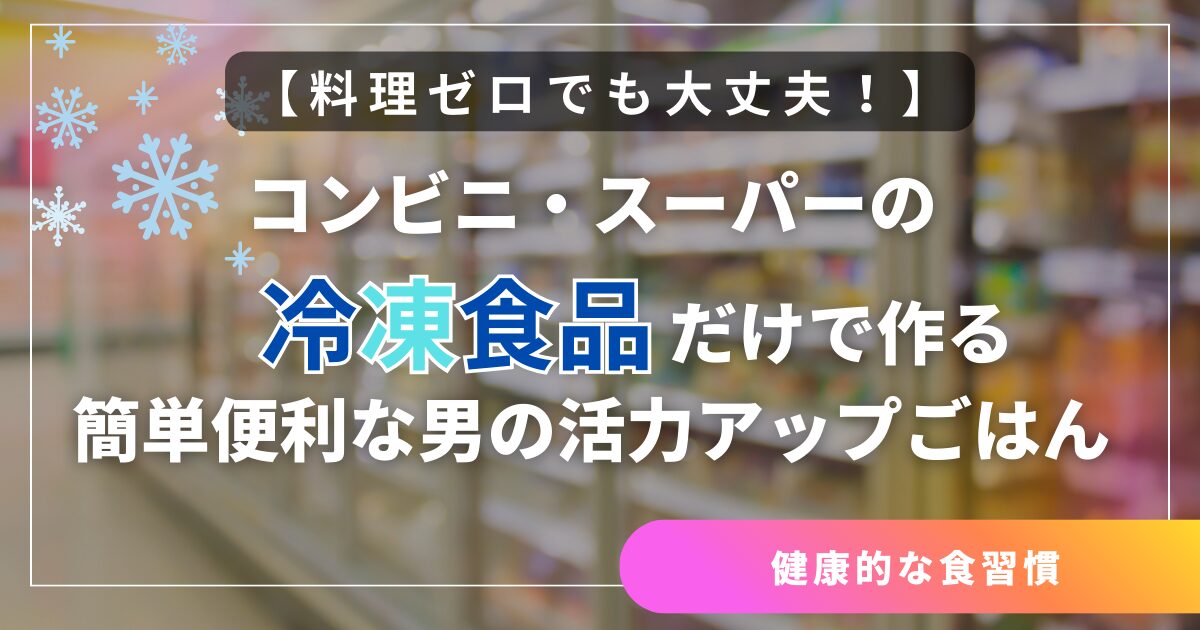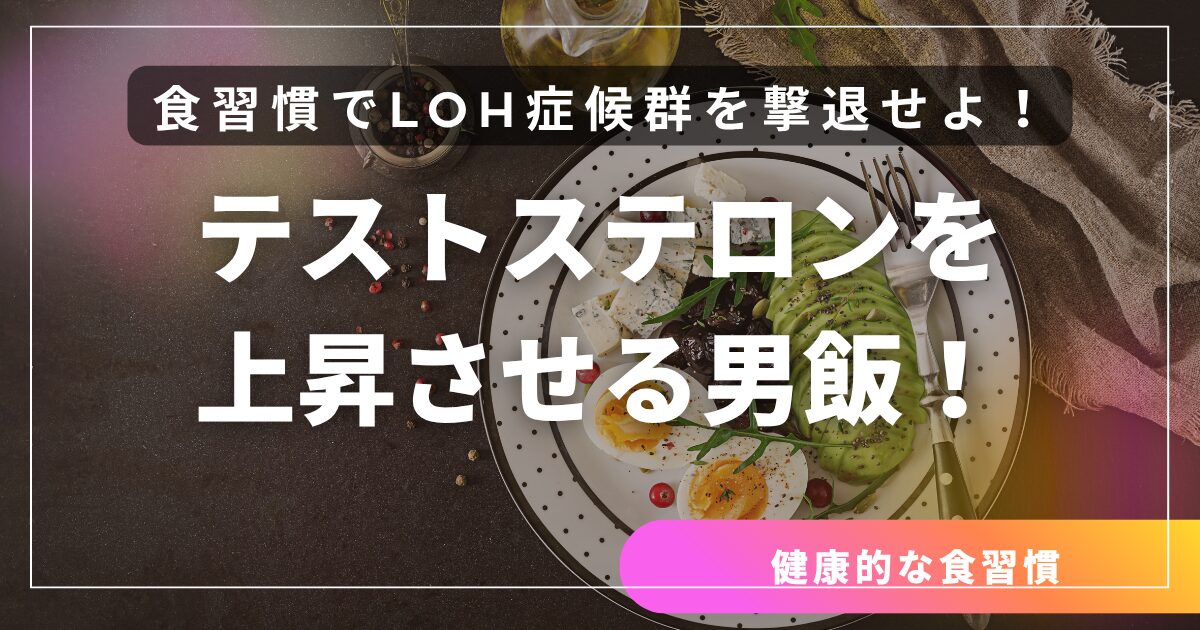その疲れ、肝臓が原因かも?男性更年期と見分けにくい「脂肪肝」の話
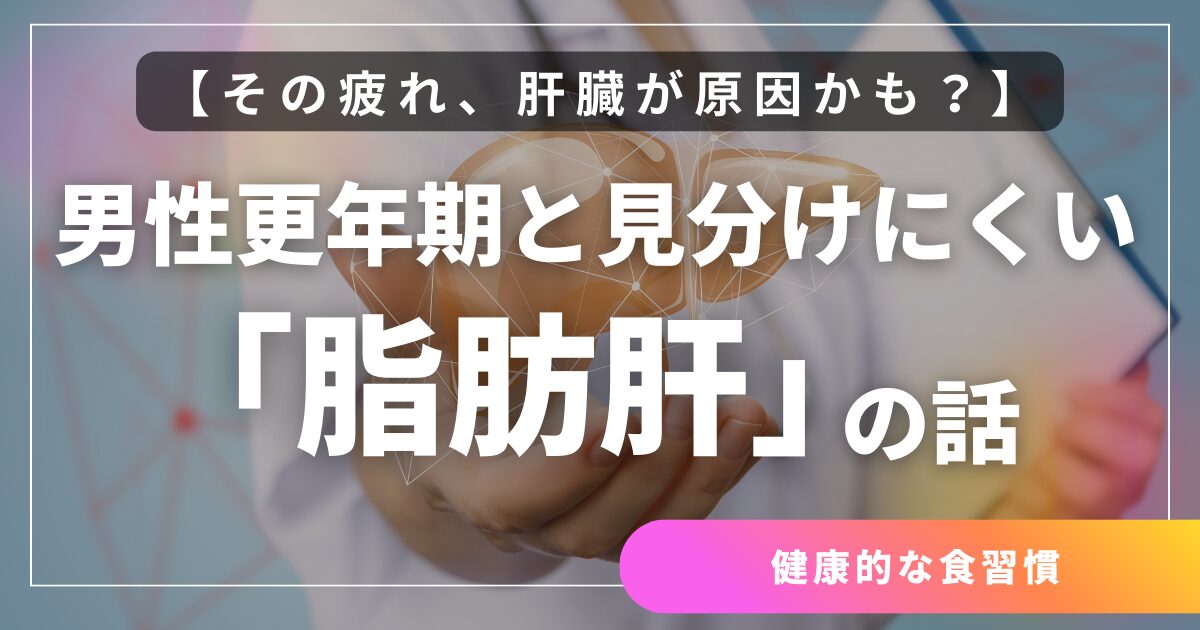
40代を過ぎてから続くその不調。いろいろ対策しているのに、いまいちスッキリしない…。そう感じていませんか?
その原因、もしかしたら男性ホルモンだけでなく、「肝臓」からの隠れたサインかもしれません。
健康診断で「脂肪肝」や「肝機能の数値が少し高い」と指摘されても、「お酒はあまり飲まないから大丈夫」と見過ごしてはいないでしょうか。
実は今、お酒が原因ではない「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD(ナッフルド))」が、働き盛りの40〜60代男性に急増しており、3人に1人が当てはまると言われています。
このNAFLDによる「だるさ」や「疲労感」は、男性更年期の症状と非常によく似ているため、本当の原因が見逃されがちです。
この記事を読めば、あなたの不調の根本原因かもしれない「肝臓」の状態を改善するための、科学的根拠に基づいた具体的な対策が分かります。
えっ、だるいのって更年期だけが原因じゃないんすか? 肝臓も関係あるとか、ややこしいっすね…。

そうなの。症状が似ているから、原因を勘違いしやすいのよ。

あぁ、その通りだ。男の不調はホルモンだけじゃない。肝臓は“沈黙の臓器”だが、疲れやだるさとして悲鳴を上げていることもある。見直すべきが生活習慣だって点は同じだからな。

その不調、更年期だけじゃない?「脂肪肝」が男性の元気を奪う3つの理由
理由1:体の「エネルギー工場」が機能不全を起こすから
肝臓は、食事から得た栄養をエネルギーに変える、体の一大工場です。しかし、脂肪肝になると工場の機能が低下し、エネルギーを効率よく作り出せなくなります。
その結果、体は常に「ガス欠」のような状態に。これが、原因のよくわからない疲労感やだるさとなって現れます。
理由2:増えた脂肪が「男性ホルモンを減らす」から
脂肪肝とセットで増えやすいのが、お腹周りの内臓脂肪です。実はこの脂肪細胞、男性ホルモンを女性ホルモンに変えてしまう「アロマターゼ」という酵素を放出します。
つまり、脂肪が増えれば増えるほど、男性としての活力を支えるテストステロンが減ってしまうという悪循環に。これが、意欲の低下や性欲の減退といった、男性更年期そっクリの症状につながるのです。
理由3:全身に広がる「じわじわ炎症」が脳を疲れさせるから
脂肪が溜まった肝臓は、体内で「慢性的な炎症」を引き起こします。この“じわじわと広がる小さな火事”のような状態は、テストステロンを作る精巣の働きを弱らせるだけでなく、炎症物質が脳にも影響を与えます。
その結果、気分の落ち込みや集中力の低下、強い倦怠感など、精神的な不調が出やすくなるのです。
このように、脂肪肝を放置することは、肝臓だけでなく男性としての心身のバランス全体を崩す原因になります。
肝臓をケアすることは、男性更年期のつらい症状を和らげるための、非常に重要なアプローチなのです。
日本人中年男性に多い「NAFLD(ナッフルド)」とは
NAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患)は、その名のとおりアルコールが原因ではない脂肪肝のことを指します。
原因は主に「生活習慣」。とくに以下の要因が重なると、肝臓に脂肪がたまりやすくなります。
一見「太っていない人」でも、内臓脂肪が蓄積していればNAFLDになることがあります。これを「隠れ脂肪肝」と呼びます。
健康診断の「ALT・AST」は肝臓からのSOSサイン

健康診断の結果票に並んでいるALT(GPT)やAST(GOT)。これらは肝臓の状態をチェックする基本的な数値です。
これらの数値が高いと、肝細胞がダメージを受けて酵素が血液中に漏れ出していることを意味します。
特にALTが高い場合は、脂肪肝やNAFLDの可能性が高いとされます。
つまりALTが上がってきたら「肝臓が助けてくれ!」ってサインを出してるってことだな。

ALT・ASTはあくまで“入り口”の指標ですが、健康診断で要注意になったら放置せず、「生活習慣を変えるタイミングが来た」と考えることが大切です。
まずは体重を7〜10%落とすだけで変わる
NAFLD改善のために医師やガイドラインが口をそろえて言うのが、「体重の7〜10%減少」です。
体重70kgの人なら、目標は約5〜7kg減。これは、数ヶ月かけて達成すれば十分です。
無理なダイエットは必要ありません。
え、7%っすか? ダイエットって10kgとか一気に落とさないと意味ないって思ってました…。

研究では、体重のわずか7%を減らすだけで、肝臓の脂肪はしっかり減少することが確認されているのよ。つまり「小さな頑張りでも、肝臓はちゃんと応えてくれる」ということね。

少しの減量でOK!体重と脂肪肝の密接な関係

なぜ体重を減らすと肝臓に良いのでしょうか? 理由はシンプルです。
食事で摂りすぎたカロリーは「内臓脂肪」として蓄えられ、そこから溢れ出た脂肪が肝臓に流れ込んでしまいます。すると、肝臓の細胞が脂肪でパンパンになり、やがて細胞壁が壊れ、細胞の中にあったALTやASTが血液中に漏れ出します。
これが健康診断でALTやASTの数値が上がる原因です。
しかし、肝臓は回復力が高い臓器。体重を少し減らすだけで、溜まった脂肪はエネルギーとして使われ始め、肝機能は改善に向かうのです。
実際に、多くの信頼できる研究でも、嬉しい変化が報告されています。
- 体重の5%減少で… 肝臓の脂肪が減り始める
- 7〜10%減少で… 肝臓の数値(ALTなど)や炎症が改善する
- 10%以上減少で… より進行した危険な脂肪肝(NASH)の改善も期待できる
つまり減量は、健康診断の数値を下げる最も確実な近道なのです。
5%から効果があるんですね!オレの体重が70kgだから…たった3.5kgか。それなら、なんだかできそうな気がしてきました!

ええ、素晴らしい気づきね。最初から「10kg減らすぞ!」と意気込むより、まずはその「最初の3kg」を目指すのが、成功の秘訣よ。

挫折しない!「続けられる」減量ゴールの立て方

ダイエットで一番難しいのが「続けること」。無理な目標を立てて三日坊主…そんな経験、誰にでもあるはずです。
でもご安心ください。肝臓のための減量は、無理なく、そして確実に結果を出すためのコツがあります。
コツ1:目標は「月に1kg減」で十分!
理想は、1ヶ月に体重の1〜2%減のペース(70kgなら0.7〜1.4kg)。焦らず「月に1kg」と考えるだけで、心の負担がぐっと軽くなります。
コツ2:「いつもの食事」から少しだけ引いてみる
毎日500kcal減らすのが目標ですが、これは「夕食のご飯を半分にする」「揚げ物を焼き魚に変える」といった小さな工夫で達成できます。
コツ3:「やめる」のではなく「置き換える」
「ガマン」は続きません。「夜食のラーメンを春雨スープに」「甘い缶コーヒーをブラックに」など、よりヘルシーなものに置き換えることから始めてみましょう。
このペースなら、数ヶ月後には無理なく目標体重が見えてきます。大事なのはスピードよりも「習慣にすること」です。
「焦らず、されど着実に」だ。小さな一歩の積み重ねが、数ヶ月後には大きな変化になる。肝臓はその努力を裏切らんぞ。

科学が認めた! 肝臓がみるみる若返る「最強の食事術」

NAFLD改善の最大のカギ、それは「食習慣の見直し」です。
最新の研究では「何を、どう食べるか」が、肝臓の脂肪や炎症に直接影響することが分かっています。
やっぱり食事ですか…。正直、夜の唐揚げとビールが一番の楽しみなんですけど…やっぱりダメですよね…。

その組み合わせ、肝臓にとっては悲鳴ものね…。でも大丈夫。少し工夫するだけで、食事は肝臓の最高の味方になります。所長、科学的な裏付けのある方法を紹介しましょう!

よし来た!遠回りな根性論より、科学的な近道を知るのが一番だ!

地中海食を超える?「グリーン・地中海食」の力

海外の研究で、肝脂肪を約40%も減少させると話題になったのが「グリーン・地中海食」です。
その内容は、従来の地中海食に「緑茶、くるみ」をプラスし、「赤身肉をあまり食べない」というシンプルなもの。抗酸化作用の強いポリフェノールをたくさん含んだ食材を組み合わせるのがポイントです。
地中海食に以下の要素を加えたのが「グリーン地中海食」です。
- 間食にくるみを30g程度
- 緑茶を1日3〜4杯
- 地中海食に比べさらに赤身肉を控える(タンパク質は主に魚介類)
なんか意外とできそうっすね! 魚とナッツと緑茶なら好きっす!

最も手軽で効果大!「甘い飲み物」をやめてみる
清涼飲料水やお菓子に潜む果糖(フルクトース)は、肝臓でダイレクトに脂肪へ変わりやすい、いわば“脂肪の素”。
ある研究では、果糖を控えるだけで、体重は変わらなくても肝脂肪だけが減少したという驚きの結果も出ています。
つまり、いつもの飲み物を水やお茶に置き換えるだけでも、肝臓の負担は劇的に減らせるのです。
コーラやジュースをやめて水やお茶に変えるだけで、数値が改善する人は多いんだぞ!

えっ、それならオレも今日から緑茶に変えます!

抗炎症食で肝臓と全身の炎症を抑える
NAFLDの本当に怖いところは、単に脂肪がたまるだけでなく、肝臓の中で「慢性的な炎症」という“小さな火事”が常にくすぶっている点です。
この火事を消し、肝臓をダメージから守ってくれるのが「抗炎症作用」を持つ食べ物です。
特別な食事は必要ありません。日々の食卓で、以下の3つを意識することから始めてみましょう。
- 週に2〜3回は魚、特にサバやイワシなどの青魚を食べる
- 主食の白米を、玄米や雑穀米、全粒粉パンに置き換えてみる
- 緑黄色の葉物野菜(ほうれん草など)を1日に350g以上(両手に山盛り一杯が目安)摂る
この食生活は、肝臓だけでなく、心臓病や糖尿病といった生活習慣病の予防にも繋がります。まさに、体全体を元気にするための食事法ですね!

「油抜き」は間違い!“良い油”と“第二の肝臓”を育てる食事術

「脂肪を減らしたいから、油は全面カット!」…もし、そう考えていたら、それは逆効果かもしれません。本当に避けるべきは、揚げ物やスナック菓子に含まれる酸化した“悪い油”です。
逆に、オリーブオイル、ナッツ、青魚などに含まれる“良い油(不飽和脂肪酸)”は、積極的に摂りたい味方。肝臓の炎症を抑え、溜まった脂肪を減らすのを助けてくれます。
そして、もう一つ絶対に欠かせないのが「たんぱく質」です。 なぜなら、たんぱく質が育てる筋肉こそ、肝臓の負担を減らしてくれる「第二の肝臓」だからです。
筋肉は、血液中の余分な糖を処理してくれる巨大なタンクの役割を果たします。
筋肉量が増えれば、糖が肝臓に流れ込んで脂肪に変わるのを防ぎ、肝臓を根本から休ませることができるのです。
なるほど!「唐揚げの油」と「サバの脂」が違うのは分かりましたけど、まさか筋肉まで肝臓に関係してるとは…!

ええ。良い油で肝臓の炎症を抑え、たんぱく質で“第二の肝臓”を育てる。この両輪でアプローチするのがとても効果的なのよ。

今日から始める!肝臓をいたわる「食事の黄金ルール」
「理論は分かったけど、具体的に何をすればいいの?」…ごもっともです。
ここからは、これまでの内容を凝縮した、誰でも今日から実践できる「食事の黄金ルール」を紹介します。
所長、オレ料理とか全然しないんですけど…それでもできますか?

おう、任せとけ!大切なのは「足し算」と「引き算」だ。難しいことは何もない!

黄金ルール:いつもの食事に「魚・豆・野菜」を足し、「甘い飲み物」を引く
これまでの話をまとめると、やるべきことは非常にシンプルです。
- 魚・豆製品: 「第二の肝臓」である筋肉の材料(たんぱく質)
- 野菜・きのこ・海藻: 肝臓の炎症を抑え、糖の吸収を穏やかにする
- ナッツ・オリーブオイル: 肝脂肪を減らす“良い油”
- ジュース・加糖コーヒーなどの甘い飲み物: 肝臓で脂肪に直結する「果糖」
まずはこの「足し算」と「引き算」だけを意識してください。
これだけで、これまで解説した4つの食事法(グリーン地中海食、脱・甘い飲み物、抗炎症食、良い油+たんぱく質)の要点を、自然と実践できます。
実践編①:コンビニ・外食では「定食スタイル」を目指す
忙しい平日、昼食はコンビニ弁当や外食になりがち。でも選び方を変えるだけで肝臓の負担はぐっと減らせます。
ポイントは「一汁三菜」をイメージすることです。
- 丼物なら「牛丼大盛り」ではなく「定食+ご飯小盛り」
- 揚げ物ではなく、焼き魚や蒸し鶏を選ぶ
- サラダやカット野菜を必ず一品プラス
- スープは具だくさん味噌汁や野菜スープを選ぶ
- コンビニなら「サバ塩焼き+ほうれん草のおひたし+豚汁+おにぎり」
つまり、炭水化物と脂質に偏った食事を「たんぱく質+野菜」へシフトさせるのがポイントです。
牛丼にサラダをつけるだけでも違うんすか?

その通り!完璧じゃなくても、一品でも「魚・豆・野菜」をプラスする意識が、肝臓を大きく変えていくのよ。

実践編②:「飲み物」と「間食」を肝臓の味方に変える
飲み物と間食は、意外と「隠れカロリー」や「果糖」が多いポイントです。ここを変えると数値改善が早まります。
- ジュースや缶コーヒーは水・緑茶・ブラックコーヒーに置き換える
- 間食はナッツ一握りや無糖ヨーグルトがおすすめ
- 寝る前のアルコールは週に2〜3回は休肝日をつくる
こうした工夫を積み重ねることで、体重や肝脂肪は自然に減っていきます。
特に「甘い飲み物」をやめるだけで、数週間で体重がスッと落ちる人は多い。効果は絶大だぞ。

「いきなり全部」は大変なので、まずは「甘い飲み物」をやめてみることから始めてみるといいですね。

食事改善の次の一手 科学的に見るサプリ&腸活(プロバイオティクス)
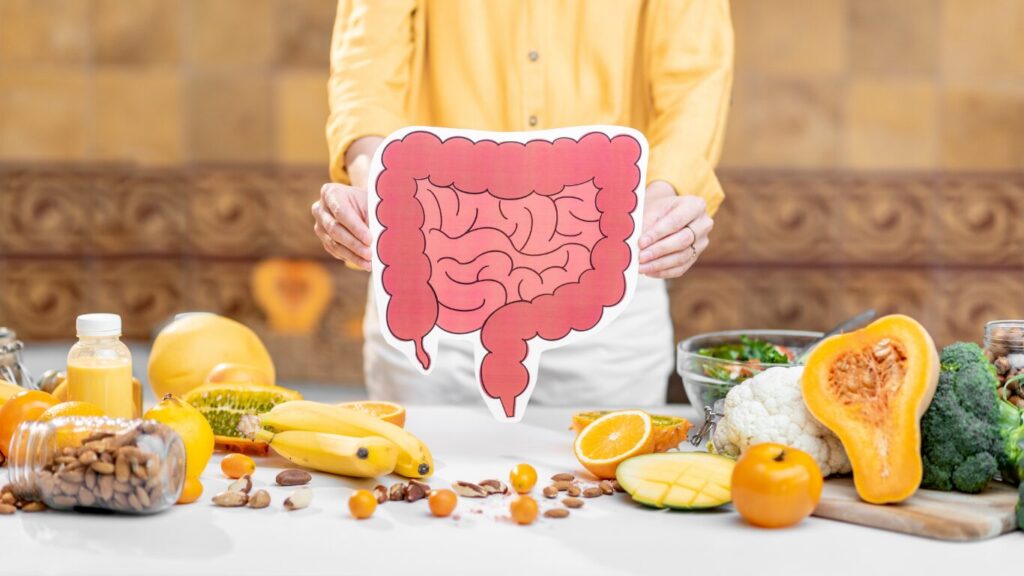
NAFLD対策の基本は、あくまで食事改善と運動です。
その上で、「さらなる改善を目指すため」の選択肢として、サプリメントやプロバイオティクスが科学的にも注目されています。
所長、サプリって効くんすか? なんか広告とかいっぱいあって迷うんですけど…。

いい質問だ! 「効くもの」と「根拠が足りないもの」があるから、そこをちゃんと見極めるのが大事だぞ!

そうですね。今回は、信頼できる研究で効果が示されているものに絞って紹介しますね。

まず注目すべきは「腸活」:腸内環境が肝臓の運命を握る
あまり知られていませんが、腸と肝臓は「門脈」という血管で直結しており、腸内環境が悪化すると、悪玉菌が作る有害物質がダイレクトに肝臓へ流れ込み、脂肪肝を悪化させます。
逆に言えば、腸内環境を整えること(腸活)は、肝臓を守ることに直結するのです。
例えば、ある信頼できる研究では、乳酸菌やビフィズス菌など複数菌株を含むプロバイオティクスを摂取したグループで、以下のような効果が確認されています。
- 肝臓の脂肪量が明らかに減少
- 体内の炎症レベルが低下
- 善玉菌が増え、腸内環境が改善
ヨーグルトやサプリメントで善玉菌を補給する「腸活」は、肝臓にとって心強いサポートになります。
腸活についてはコチラで詳しく解説していますよ♡

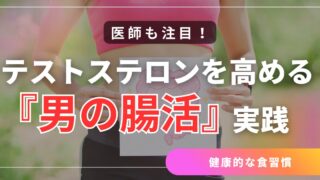
ビタミンEや一般サプリとの「賢い付き合い方」

ビタミンEは、その強い抗酸化作用から、炎症を伴う進行した脂肪肝(NASH)に対する有効性が報告されています。
しかし、自己判断での過剰摂取は健康リスクを伴うため、必ず医師の指導が必要です。
また、「肝臓の数値を下げる!」とうたうサプリは世に多くありますが、中には科学的根拠が乏しいものも少なくありません。
「これさえ飲めば大丈夫」という謳い文句には、まず注意が必要です。
基本は食習慣の改善と運動。サプリはあくまで「補助」として位置づけましょう。
サプリは魔法じゃない。大事なのは食事と運動で土台を整えることだな。

なるほど!まずは食事と運動。それでも足りない部分があれば、根拠のあるサプリで補うってことですね!

体重計は気にしない!運動が肝臓に「直接」効く理由

最新の研究では、体重が大きく変わらなくても、運動するだけで肝臓の脂肪は減っていくことが分かっています。
大切なのは体重計の数字ではありません。あなたの体の中で起きている「良い変化」です。
えっ、マジですか!?体重が動かなくても、肝臓はちゃんと良くなってるんですか?

ええ。実際に、自宅でできるレベルの運動を続けるだけで、体重は変わらなくても肝脂肪が明らかに減少したというちゃんとした研究報告があるのよ。

体重が落ちなくても肝脂肪は減る3つの良い変化
- 肝臓の“脂肪燃焼エンジン”がフル稼働! 有酸素運動は、肝臓や筋肉の細胞内にある「ミトコンドリア(脂肪燃焼エンジン)」を活性化させます。これにより、肝臓に溜まった脂肪がエネルギーとしてどんどん燃焼され始めます。
- “第二の肝臓(筋肉)”が糖を吸い取ってくれる! 筋トレで筋肉が増えると、食事で摂った糖を筋肉が効率よく処理してくれます。その結果、糖が肝臓へ流れ込んで脂肪に変わるのを防ぎ、肝臓の仕事を大きく助けてくれるのです。
- 肝臓でくすぶる“小さな火事(炎症)”を鎮火する! 運動には、全身の炎症を抑える効果があります。脂肪肝の悪化原因である「慢性的な炎症」を鎮め、肝臓を守ってくれます。
今日から始める!自宅でできる「肝臓リセット運動プラン」

専門家が推奨するのは「有酸素運動(週150分)+筋トレ(週2〜3回)」の組み合わせです。一度にやる必要はなく、スキマ時間で分割してOKです!
- 平日: 通勤時や昼休みに「やや息が上がる」ペースの速歩きを1日20分。
- 休日: 少し長めに30〜40分のウォーキングやサイクリングを楽しむ。
- 時短ワザ: 「3分速歩き+2分ゆっくり歩き」を5セット繰り返すインターバル速歩も効果的です(合計25分)。
「あと2〜3回ならできるかも」くらいの負荷がベストです。ペットボトルをダンベル代わりにしてもOK!
- スクワット: 10〜15回(椅子に座る直前まで腰を落とす)
- 腕立て伏せ: 8〜12回(壁や机に手をついてOK)
- プランク: 20〜40秒キープ
運動については以下の記事で詳しく説明しています。ぜひご参考になさってください♡


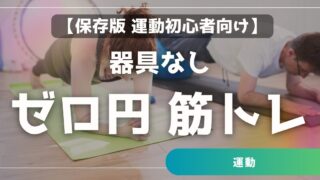
【デスクワーカー必見】座りすぎ防止の“ちょい足し運動”
60分に一度は立ち上がり、1〜2分歩き回る、トイレに行く、階段を一段上り下りするなど、とにかく座りっぱなしを中断させましょう。これだけでも血糖値のコントロールに役立ちます。
これなら、特別な時間を作らなくても“ながら”でできそうですね!会議前にこっそりスクワットとか…!

いいじゃないか!肝臓が喜ぶなら、どんどんやれ!

挫折しないための3つのルール
三日坊主で終わらせないための、簡単なルールです。
- 安全第一!無理はしないこと
胸の痛みやめまいがあれば、まず医師に相談を。膝や腰が痛む場合は無理せず、やり方や負荷を見直しましょう。 - 生活に溶け込ませる
「歯磨きの前にスクワット」「お風呂の前にプランク」など、毎日の習慣とセットにすると忘れずに続けられます。 - 頑張りを“見える化”する
スマホのヘルスケアアプリで歩数を記録するだけでも、モチベーションに繋がります。頑張った記録は、あなたを裏切りません。
スマートウォッチの活用法については以下の記事をご覧下さい。おすすめのスマートウォッチも紹介していますよ♡

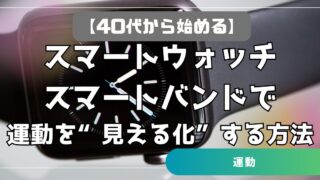
まとめ 未来の自分のために、今日から始める小さな習慣

「なんとなく続く不調」の原因が、男性更年期だけでなく「沈黙の臓器」である肝臓にある可能性、そしてその対策が決して難しいものではないことをお伝えしてきました。
NAFLDの改善に必要なのは、厳しい食事制限やハードなトレーニングではありません。日々の生活における「少し賢い選択」の積み重ねです。
この記事でお伝えした大切なポイントを、最後にもう一度だけ振り返ります。
- 目標は「月に1kg」のゆるい減量から
まずは現在の体重から5〜7%減らすことを目指しましょう。焦る必要は一切ありません。 - 食事は「足し算・引き算」で考える
何よりもまず「甘い飲み物」をやめる(引き算)。そして、いつもの食事に「魚・豆・野菜」をプラスする(足し算)。この意識が、肝臓を大きく変えます。 - 運動は「体重計」を気にせず続ける
まずは1日15分の速歩きから。その一歩一歩が、体重計の数字とは関係なく、あなたの肝臓の脂肪を直接燃やしてくれます。
まずはたった一つでも構いません。今日からできることを見つけて、ぜひ始めてみてください。
肝臓は、あなたが思っている以上に回復力のある、頼もしいパートナーです。あなたの小さな努力に、必ず応えてくれます。
半年後、一年後のエネルギッシュな自分のために、今日、最初の一歩を踏み出しましょう。
肝臓は沈黙の臓器。症状が出たときには進んでいることが多いんだ。

うわ…怖いっすね。でも逆に、今のうちに動けば間に合うってことっすよね!

そのとおり。今始めれば、未来の肝臓を救えるはずです!

専門医を受診すべきタイミング

NAFLDは放置するとNASH(炎症を伴う脂肪肝)や肝硬変に進展することもあります。
次のような場合は早めに専門医(消化器内科・肝臓内科)の受診を検討してください。
- ALT・ASTが正常値の2倍以上続いている
- 体重減少や生活改善でも数値が改善しない
- 血糖・中性脂肪・コレステロールも一緒に悪化している
- 強い疲労感や黄疸など、明らかな症状が出てきた
専門医による画像検査や詳細な血液検査で、進行度を確認できます。
「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにせず、早めのチェックをおすすめします。
参考リンク
この記事の参考論文はコチラ
Bischoff SC, Bernal W, Dasarathy S, Merli M, Plank LD, Schütz T, Plauth M. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in liver disease. Clin Nutr. 2020 Dec;39(12):3533-3562. doi: 10.1016/j.clnu.2020.09.001. Epub 2020 Oct 27. PMID: 33213977.
Evans M, Antony J, Guthrie N, Landes B, Aruoma OI. A Randomized Double-Blind, Placebo Controlled, Four-Arm Parallel Study Investigating the Effect of a Broad-Spectrum Wellness Beverage on Mood State in Healthy, Moderately Stressed Adults. J Am Coll Nutr. 2018 Mar-Apr;37(3):234-242. doi: 10.1080/07315724.2017.1393356. Epub 2018 Jan 9. PMID: 29313751.
Fuster V. Changing Our Dietary Habits: Empathizing With Sisyphus. J Am Coll Cardiol. 2017 May 30;69(21):2665-2667. doi: 10.1016/j.jacc.2017.04.021. PMID: 28545641.
Juan S, Lee JH, Won SJ, Oh S, Ha MS. Effect of Saengmaeksan on Fatigue, Liver Function, and Immunity Combined with High-Intensity Training. J Immunol Res. 2023 Jun 30;2023:3269293. doi: 10.1155/2023/3269293. PMID: 37425492; PMCID: PMC10328733.
Kenđel Jovanović G, Mrakovcic-Sutic I, Pavičić Žeželj S, Benjak Horvat I, Šuša L, Rahelić D, Klobučar Majanović S. Metabolic and Hepatic Effects of Energy-Reduced Anti-Inflammatory Diet in Younger Adults with Obesity. Can J Gastroenterol Hepatol. 2021 Feb 5;2021:6649142. doi: 10.1155/2021/6649142. PMID: 33628758; PMCID: PMC7886596.
Kwon OY, Lee MK, Lee HW, Kim H, Lee JS, Jang Y. Mobile App-Based Lifestyle Coaching Intervention for Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res. 2024 Feb 15;26:e49839. doi: 10.2196/49839. Erratum in: J Med Internet Res. 2024 Feb 27;26:e57499. doi: 10.2196/57499. PMID: 38358794; PMCID: PMC10905353.
Simons N, Veeraiah P, Simons PIHG, Schaper NC, Kooi ME, Schrauwen-Hinderling VB, Feskens EJM, van der Ploeg EMCL, Van den Eynde MDG, Schalkwijk CG, Stehouwer CDA, Brouwers MCGJ. Effects of fructose restriction on liver steatosis (FRUITLESS); a double-blind randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2021 Feb 2;113(2):391-400. doi: 10.1093/ajcn/nqaa332. PMID: 33381794; PMCID: PMC7851818.
Sirisunhirun P, Bandidniyamanon W, Jrerattakon Y, Muangsomboon K, Pramyothin P, Nimanong S, Tanwandee T, Charatcharoenwitthaya P, Chainuvati S, Chotiyaputta W. Effect of a 12-week home-based exercise training program on aerobic capacity, muscle mass, liver and spleen stiffness, and quality of life in cirrhotic patients: a randomized controlled clinical trial. BMC Gastroenterol. 2022 Feb 14;22(1):66. doi: 10.1186/s12876-022-02147-7. PMID: 35164698; PMCID: PMC8845268.
Yaskolka Meir A, Rinott E, Tsaban G, Zelicha H, Kaplan A, Rosen P, Shelef I, Youngster I, Shalev A, Blüher M, Ceglarek U, Stumvoll M, Tuohy K, Diotallevi C, Vrhovsek U, Hu F, Stampfer M, Shai I. Effect of green-Mediterranean diet on intrahepatic fat: the DIRECT PLUS randomised controlled trial. Gut. 2021 Nov;70(11):2085-2095. doi: 10.1136/gutjnl-2020-323106. Epub 2021 Jan 18. PMID: 33461965; PMCID: PMC8515100.
Abbie E, Francois ME, Chang CR, Barry JC, Little JP. A low-carbohydrate protein-rich bedtime snack to control fasting and nocturnal glucose in type 2 diabetes: A randomized trial. Clin Nutr. 2020 Dec;39(12):3601-3606. doi: 10.1016/j.clnu.2020.03.008. Epub 2020 Mar 13. PMID: 32204977.
Cukoski S, Lindemann CH, Arjune S, Todorova P, Brecht T, Kühn A, Oehm S, Strubl S, Becker I, Kämmerer U, Torres JA, Meyer F, Schömig T, Hokamp NG, Siedek F, Gottschalk I, Benzing T, Schmidt J, Antczak P, Weimbs T, Grundmann F, Müller RU. Feasibility and impact of ketogenic dietary interventions in polycystic kidney disease: KETO-ADPKD-a randomized controlled trial. Cell Rep Med. 2023 Nov 21;4(11):101283. doi: 10.1016/j.xcrm.2023.101283. Epub 2023 Nov 7. PMID: 37935200; PMCID: PMC10694658.
Gillingham MB, Elizondo G, Behrend A, Matern D, Schoeller DA, Harding CO, Purnell JQ. Higher dietary protein intake preserves lean body mass, lowers liver lipid deposition, and maintains metabolic control in participants with long-chain fatty acid oxidation disorders. J Inherit Metab Dis. 2019 Sep;42(5):857-869. doi: 10.1002/jimd.12155. Epub 2019 Jul 24. PMID: 31295363; PMCID: PMC7452215.
Goss AM, Dowla S, Pendergrass M, Ashraf A, Bolding M, Morrison S, Amerson A, Soleymani T, Gower B. Effects of a carbohydrate-restricted diet on hepatic lipid content in adolescents with non-alcoholic fatty liver disease: A pilot, randomized trial. Pediatr Obes. 2020 Jul;15(7):e12630. doi: 10.1111/ijpo.12630. Epub 2020 Mar 4. PMID: 32128995.
Iwasa M, Iwata K, Hara N, Hattori A, Ishidome M, Sekoguchi-Fujikawa N, Mifuji-Moroka R, Sugimoto R, Fujita N, Kobayashi Y, Takei Y. Nutrition therapy using a multidisciplinary team improves survival rates in patients with liver cirrhosis. Nutrition. 2013 Nov-Dec;29(11-12):1418-21. doi: 10.1016/j.nut.2013.05.016. PMID: 24103520.
Kalal C, Benjamin J, Shasthry V, Kumar G, Sharma MK, Joshi YK, Sarin SK. Effect of long-term aggressive nutrition therapy on survival in patients with alcohol-related cirrhosis: A randomized controlled trial. Indian J Gastroenterol. 2022 Feb;41(1):52-62. doi: 10.1007/s12664-021-01187-3. Epub 2022 Mar 2. PMID: 35235198.
Moctezuma-Velázquez C, García-Juárez I, Soto-Solís R, Hernández-Cortés J, Torre A. Nutritional assessment and treatment of patients with liver cirrhosis. Nutrition. 2013 Nov-Dec;29(11-12):1279-85. doi: 10.1016/j.nut.2013.03.017. Epub 2013 Jul 16. PMID: 23867207.
Mogna-Peláez P, Riezu-Boj JI, Milagro FI, Herrero JI, Elorz M, Benito-Boillos A, Tobaruela-Resola AL, Tur JA, Martínez JA, Abete I, Zulet MA. Inflammatory markers as diagnostic and precision nutrition tools for metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease: Results from the Fatty Liver in Obesity trial. Clin Nutr. 2024 Jul;43(7):1770-1781. doi: 10.1016/j.clnu.2024.05.042. Epub 2024 May 31. PMID: 38861890.
Qanavati M, Sarrami L. The Impact of Eight Weeks of Moderate-Intensity Aerobic Exercise and Nutrition with a Traditional Iranian Medicine Approach on Liver Enzymes in Young Boys. Adv Mind Body Med. 2024 Spring;38(2):4-9. PMID: 38837776.
Li Y, Li X. Nutritional assessment and factors affecting dietary intake in patients with cirrhosis: a single-center observational study. Nutrition. 2022 May;97:111224. doi: 10.1016/j.nut.2021.111224. Epub 2021 Mar 3. PMID: 33838983.
Trouwborst I, Gijbels A, Jardon KM, Siebelink E, Hul GB, Wanders L, Erdos B, Péter S, Singh-Povel CM, de Vogel-van den Bosch J, Adriaens ME, Arts ICW, Thijssen DHJ, Feskens EJM, Goossens GH, Afman LA, Blaak EE. Cardiometabolic health improvements upon dietary intervention are driven by tissue-specific insulin resistance phenotype: A precision nutrition trial. Cell Metab. 2023 Jan 3;35(1):71-83.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2022.12.002. PMID: 36599304.
Wernicke C, Pohrt A, Pletsch-Borba L, Apostolopoulou K, Hornemann S, Meyer N, Machann J, Gerbracht C, Tacke F, Pfeiffer AF, Spranger J, Mai K. Effect of unsaturated fat and protein intake on liver fat in people at risk of unhealthy aging: 1-year results of a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2023 Apr;117(4):785-793. doi: 10.1016/j.ajcnut.2023.01.010. Epub 2023 Jan 13. PMID: 36804020.